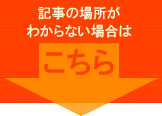|
|
 |

近場にある岡本太郎と日本の古民家
| 出掛ける場所を提案する、港北NTオートのドライブレポート第二弾 | 2006/07/01 |

■テーマ - 「宿場」
宿場にある3つの家は、どれも立派なものだ。油屋を営んでいた井岡家は17〜18世紀の奈良に建てられたとされるが、強風に耐えるべく瓦屋根を持ち、今で言うセキュリティ面での対策も当時なりに施してある。
三澤家は、この「宿場」では最も大きな家で、薬屋を営んでいたその当時の看板も残される19世紀中期の長野に建てられた家。家柄の面で門などを構えることが許されたのも大きな特徴である。
 この鈴木家は「奥の細道」でも知られる奥州街道沿いにあった馬宿。19世紀の初頭に福島市に建てられたものだ。その機能は当初馬宿であったのは間違いない。構造的には今の駐車場のような部分が屋内にあり、ロバ程度の大きさになった馬を繋いでおくようになっている。せりに出すために馬を連れた飼い主が、ここで宿をとり、あくる朝に市場へ出掛ける。やがて宿泊客はこの宿に娯楽を求めるようになる。 この鈴木家は「奥の細道」でも知られる奥州街道沿いにあった馬宿。19世紀の初頭に福島市に建てられたものだ。その機能は当初馬宿であったのは間違いない。構造的には今の駐車場のような部分が屋内にあり、ロバ程度の大きさになった馬を繋いでおくようになっている。せりに出すために馬を連れた飼い主が、ここで宿をとり、あくる朝に市場へ出掛ける。やがて宿泊客はこの宿に娯楽を求めるようになる。
当時の娯楽に沿って、この宿は二階に賭場や遊廓としての機能を併せ持つことになった。そのため、入口付近には狭い間口を有効利用するための上げ戸を備えるが、それは3分割構造になっており、日中は上方に引き込まれる。なかなか洒落たアイデアが仕込まれていると感心する。位の高い人物は一階の座敷に宿泊する。危険で上がることはできないが、下から階段を通して二階の方向を眺めると、当時の娯楽に熱中する人々の歓声が聞こえてくるような気になる。
この家が見つかったのは、日本民家園がスタートして物件を探していたタクシーの中。運転手との会話から見つかったという。兄弟で経営する全く同じ構造の宿が隣り合わせで建っていたが、兄の物件は取り壊され無くなってしまっていた。弟物件が今ここにある。
取材記事一覧へ
|

|
|






 この鈴木家は「奥の細道」でも知られる奥州街道沿いにあった馬宿。19世紀の初頭に福島市に建てられたものだ。その機能は当初馬宿であったのは間違いない。構造的には今の駐車場のような部分が屋内にあり、ロバ程度の大きさになった馬を繋いでおくようになっている。せりに出すために馬を連れた飼い主が、ここで宿をとり、あくる朝に市場へ出掛ける。やがて宿泊客はこの宿に娯楽を求めるようになる。
この鈴木家は「奥の細道」でも知られる奥州街道沿いにあった馬宿。19世紀の初頭に福島市に建てられたものだ。その機能は当初馬宿であったのは間違いない。構造的には今の駐車場のような部分が屋内にあり、ロバ程度の大きさになった馬を繋いでおくようになっている。せりに出すために馬を連れた飼い主が、ここで宿をとり、あくる朝に市場へ出掛ける。やがて宿泊客はこの宿に娯楽を求めるようになる。